京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第12回)
2022年04月14日
京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが難関大受験に役立つ情報をお届けします。
今回ご紹介する第12回目は、河合塾近畿教務部長 佐伯淳史が関西圏の国公立大学の今春入試(前期)の振り返りをお伝えします。
国公立大前期入試を振り返る~学習積み重ね 努力報われる~
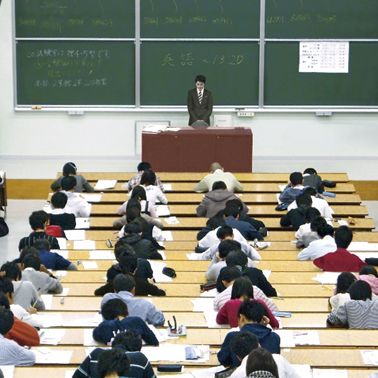
※写真は試験会場のイメージです
昨年に続き、新型コロナウイルスの影響下での実施となった2022年度入試は、何といっても「大学入学共通テスト(以下共通テスト)の平均点大幅ダウン」が大きなトピックです。手応えがなく、志望大学を変更する受験生が増えた一方で、京都大や大阪大といった共通テストの配点が低い大学は志願者を集めていました。共通テストの平均点が下がり、受験生間の点数差も小さくなったことから、結果として二次試験勝負の入試となったと言えます。その二次試験について、関西圏の大学の今春入試(前期)を振り返っていきましょう。
▶京都大は理系数学が昨年と比べ少し易しくなり、点数が取りやすくなりました。
▶英語大問Ⅳの自由英作文では、20年度は手紙形式、21年度は会話文の下線部補充、22年度は意見論述型と、ここ数年は形式が変更になっています。合格のためには、さまざまな形式の問題にふれることが必要と言えます。
▶気になる変化があったのは神戸大の英語です。「英語の文法・単語等の知識に基づき、英文を丁寧に読み解答を導く」というこれまでの日本の大学入試問題とはやや異なる設計がされています。大問Ⅱでは常識で判断するしかない問題もあり、「英文をざっくり読み、想像力を働かせながら設問に答える」ことを受験生に求める、より自由度の高い設計でした。
大阪府立大と大阪市立大が統合してできた注目の大阪公立大ですが、前期は大阪市立大をベースにしつつも、教科によっては大阪府立大入試で頻出の問題も見られました。数学に関しては理系も文系も難しくなり、今年の大阪大・神戸大入試よりも解きにくくなっています。
総じて問題の分量は増加傾向でした。形式が異なるとはいえ、大学入学共通テスト同様に情報を読み取る力の重要性が高まっています。また、各大学の難易度はやや易化傾向と言えるでしょう。丁寧に学習を積み重ねた生徒は着実に点数を取れる問題が増え、適度に差がつきやすい入試でした。努力が報われる入試になったとも言え、受験生にとっては良かったのではないでしょうか。
さて、来年以降に受験をする読者の方には、目的意識を持って勉強に取り組んでいただきたいと思います。例えば英文法の学習で言えば、文法事項を覚えることが目的ではありません。長文を速く正確に読む、英作文で正しく表現するために英文法の知識が必要になります。正しいゴール設定が学力アップに欠かせませんので、ぜひ今年の入試問題を解いてゴールを確認してみましょう。目の前の勉強が入試本番にどうつながるのかがわかれば、モチベーションも学習効率もぐっと上がるはずです。(河合塾近畿教務部長 佐伯淳史)
※本寄稿は、新聞掲載が最も遅い産経新聞社の掲載日以降に、同紙から原稿提供を受けて掲載しています。
執筆者のプロフィール

▶河合塾近畿教務部長 佐伯淳史
河合塾入職後、生徒指導や校舎運営、広報戦略立案などに携わる。天王寺校校舎長、東大・京大・医進館校舎長を歴任し、2021年4月より現職。生徒一人ひとりに最適な学習環境を提供するため、カリキュラム策定に従事。
※ 2022年4月時点
