2021年度JCERIレポート高校教育に求められる「大きな修得主義」への転換と社会活動の積極的な導入
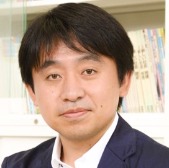
石井英真
(京都大学大学院教育学研究科)
2022年度共通テスト問題にみる学力観の転換(1/4)
学力観の転換が感じられた「共通テスト」の問題
2022年度の大学入学共通テストについて、「問題が難化した」という声が多く聞かれます。けれどもそれは、「目標の分類学」を考慮に入れていない感想であり、「難化した」と感じる理由の根幹には、テストで試される学力観の変化があると見るべきです。知識を記憶・再生する「知っている・できる」レベルから、概念を理解してつなげる「わかる」レベル、複数の知識を統合する「使える」レベルまで、学力の質は異なります。テスト問題を作成する際には、そうした学力の質を踏まえた、目標(資質・能力)の分類が重要になります。その意味では、私は必ずしも従来のセンター試験が単純な知識暗記・再生の試験だったとは思っていませんが、共通テストでは問われる思考の質が変化しました。国語では単一のテキストではなく、複数のテキストを読み比べて統合する力が求められていますし、数学や理科では生活との関連で学習内容を捉え直す形が見られました。まさに新学習指導要領で示された学力観、教科観に即した出題であり、今後もこの傾向は続くでしょう。
問題の難易度を測るもうひとつのポイント「文脈の共有」
そもそも、テストの難易度を決めるのは、知識の量と高度さ、求められる思考のプロセスだけではありません。「文脈の共有」が、もうひとつのポイントになります。同じ内容を読んでも、その分野に精通しているかどうかで、理解度が違ってくるのです。私は高校時代、京都大二次試験の国語の問題文を読んでもさっぱり分かりませんでした。でも、いまなら割とスラスラ読めます。もちろん、私の受験学力がアップしたわけではなく、研究者目線で読んでいるからです。二次試験の入試問題はその大学の教員が作成しており、ある種の学問的なメッセージがこめられています。たとえば、傍線が引かれているのは、そこが読めることが大学の学びにつながる部分です。同じく大学人の目線を共有している私には、すんなり読めるわけです。今回の共通テストも、たとえば総合的な探究の時間などで、ある種の本物体験を行った生徒にとって、解きやすい問題だったのであれば、とても良い問題だったことになります。そういった観点から、問題の中身を掘り下げて検証することが重要です。
高校教育の変化を「修得主義」で捉える(2/4)
「大きな修得主義」と「小さな修得主義」がある
今後の高校教育は、入試の変化とさほど関係なく変化していくと思われます。そもそも、大部分の高校生、特に高校1・2年生にとって、入試のプレッシャーはそれほど大きくありません。それよりもICTの活用、オンライン授業、文部科学省のGIGAスクール構想などが進行していくにつれ、修得主義に寄っていく変化の方が大きいでしょう。単に学校に通って出席したらOKではなく、高校3年間で何を学んだのかが問われるようになります。それをどう証明するのか、高校卒業認定のあり方も大きな課題になります。「学歴社会」から「学習歴社会」への転換という流れが明確になるでしょう。
ただし、修得主義イコール学びの個別化ではありません。寺子屋の自由進度学習のようなものをイメージすると、個別化のニュアンスが強くなりますが、「自主勉」と「自主ゼミ」は異なります。たとえば大学の修得主義は「自主ゼミ」の発想であり、学年は比較的ゆるやかですが、最後にゼミなどに所属し、卒業論文・研究に取り組む、いわば「大きな修得主義」になっています。卒業論文・研究を進める際には、協働性も求められ、そのあたりがちょうどいい按配になっていると感じます。一方、最後に検定試験のようなものを課して、質を保証するのが「小さな修得主義」ですが、その際も、狭い意味の学力だけでなく、人格形成を含めて、成長を保証することが大切になるというのが、私の考えです。実際、N高校(日本最大の生徒数の通信制高校)でも、単純に単位のスタンプラリーだけで卒業認定するのではなく、何らかの社会的な経験も加味して保証しようとしています。
社会活動の場を広げて「複数所属」を促進
修得主義が進めば、学年・学級が柔軟化していきます。「同期」のつながりが薄れるとまでは思いませんが、それ以外にもいろんな仲間がいて、複数に所属するようになれば、同調圧力が弱まります。学級で辛い思いをしている小中学生に逃げ場がないのは、「単一所属」だからであり、「複数所属」になれば楽になることもあるでしょう。異学年交流とか、フリーグレードみたいな話も聞かれますが、そうした形がラディカルなのではなく、「複数所属」こそがラディカルだと、私は考えています。
その意味で、私が注目しているコンセプトが、最近のいくつかの施策で掲げられた「旅する高校(生)」です。イメージはアメリカ・ミネルバ大学の教育システムですね。この大学は特定のキャンパスを持たず、4年間で世界7都市に移り住みながら、さまざまな人との出会いの中でプロジェクトをこなしていきます。それに近い形で、高校生が学校だけではなくて、学校の外側で社会活動する場が広がり、「複数所属」の形が促進されるのは、とても望ましいことです。これまでの高校生にとって、学校外の集団は、学習塾や習い事のつながりだけだったでしょう。けれども、社会活動の場こそが重要なのです。ただし、ちょっと間違えると、旅する地をスタンプラリーのように増やしただけで満足してしまう可能性があります。それで終わりでは、「小さな修得主義」になってしまいます。「大きな修得主義」との分かれ目は、その旅で何を経験し、修得するのかを明確にすることであり、そこをきちんと設計することが大切になります。
高大接続における「レディネス」(3/4)
高大接続の本質的なポイントは「レディネス」
次に、高大接続の話題に移ることにします。実は、高大接続の本質的なポイントは「レディネス(準備性)」にあると、私は考えています。大学入学後、あるいは就職後に、うまくいくだけの準備が整っているかどうか、それが接続の上でとても重要なのです。
そして、私から見れば、京都大の「特色入試」と、産業能率大のスマホ・タブレット持ち込みを可とした「未来構想方式」は、まったく違うスタイルの入試のようでいて、レディネスを問うという意味では共通している入試なのです。京都大の「特色入試」では、英文も含めて複数の資料を読み比べて、口頭試問を行います。まさに大学院入試とほぼ同じ形式が、大学入試で行われているわけです。これは京大がアカデミックレディネスを求めているためです。対して産能大は、キャリアのレディネスを強く意識して、就職試験が大学入試に降りてきた形になっています。今後、それぞれの大学が求めるレディネスを評価する入試へとシフトしていくことは間違いありません。コストの関係で、すべての入試をそうした形式にするのは困難ですが、一部だけでも実施して、レディネスを整えた層を形成することで、周囲に影響を与え、大学全体の活性化にもつながるはずです。
主体性の正体は「レディネス」である
これまでの日本では「知識」か「人物」かという二元論で語られがちで、その産物として主体性評価が生まれました。ただし、主体性を「やる気」や「自習力」と捉えるのは狭すぎます。実は主体性の正体はレディネスです。実際、面接でもポートフォリオでも、主体性評価と名づけられたものは、「やる気」よりも、「適性」を見ているでしょう。「視野が広いか」「視座が高いか」「物事をきちんと考えようとする姿勢があるか」「その物事について関心があるか」など、主体性の核心とは、その分野に対する情熱を含めたレディネスなのです。
視座を高める学習が「エージェンシー」につながる
レディネスを形成するために有効なのが、総合学習、探究学習です。視座を高めることができる学習であり、そこに総合学習、探究学習の最も大きな価値があると、私は考えています。それも、できるだけ社会活動の場を増やすことが大切です。地域の課題に大人たちが取り組んでいる姿に感化され、大人目線、あるいは玄人目線に触れ、視座が高められていくからです。その結果、認知的な面でも、全体が見渡せるようになり、いわゆる受験学力が底上げされていく部分もあると思います。
強調しておきたいのは、主体性がある大人とは、必ずしも自分で勉強する人ではないということです。「必要に応じて多様な人々と協力しながら、その中で学び取ることができる人」「自分が関心を持った対象に責任を持つ人」「直面した社会の課題が常に頭から離れない人」が、結果として主体的になっているのです。主体性とは、OECDが提唱する「エージェンシー(注)」そのものであり、周囲を巻き込みながら、社会を作り変えようとする究極の自治、自立の力です。高校時代に社会活動の機会を豊富にして、そうした本物の主体性を備えた大人と触れ合うことができれば、きわめて有意義と言えるでしょう。
まとめ
これまで高校教育がなかなか変わらなかったのは、大学入試に起因する問題以上に、社会自体が新卒一括採用の一本道だったことが大きいと思います。けれども、雇用体制は流動化、多様化が進み、横展開へと転換しています。それに応じて高校も、今までの学年主体の年齢主義から、「大きな修得主義」へと移行していくでしょう。さらに、学校における協働性のあり方も、社会活動を積極的に導入するなど、変わっていくと思われます。すでに変化の兆しが見られますが、これからの10年間はとくに変化の大きい時期に入ると予想しています。
-
注:エージェンシーについては、河合塾Guideline2021年 7・8月号を参照。
「変わる高校教育 第30回―OECD Education2030プロジェクトが掲げる『エージェンシー』の発揮される学校教育に向けて」
石井英真(いしい・てるまさ)
京都大学大学院教育学研究科 准教授。博士(教育学)。日米のカリキュラム研究、授業研究に学びながら、学校で育成すべき資質・能力の中身をどう構造化・モデル化し、カリキュラム・授業・評価・教師教育をどうデザインしていくかを研究し、学校現場の状況に応じて、先生方を応援する発信を続けている。近著に『授業づくりの深め方』(ミネルヴァ書房、2020年)、『未来の学校-ポスト・コロナの公教育のリデザイン-』(日本標準、2020年)、論考に「新学習指導要領における学習評価のあり方―観点別評価で『学びの舞台』をつくる―」『高等学校 地歴・公民科資料 ChiReKo』2021 年度3学期号(帝国書院、2020年)など。
※所属・役職は2022年3月時点のもの



![[連載]「河合塾にフォーカス](/jp/common/images/bnr-local03.jpg)